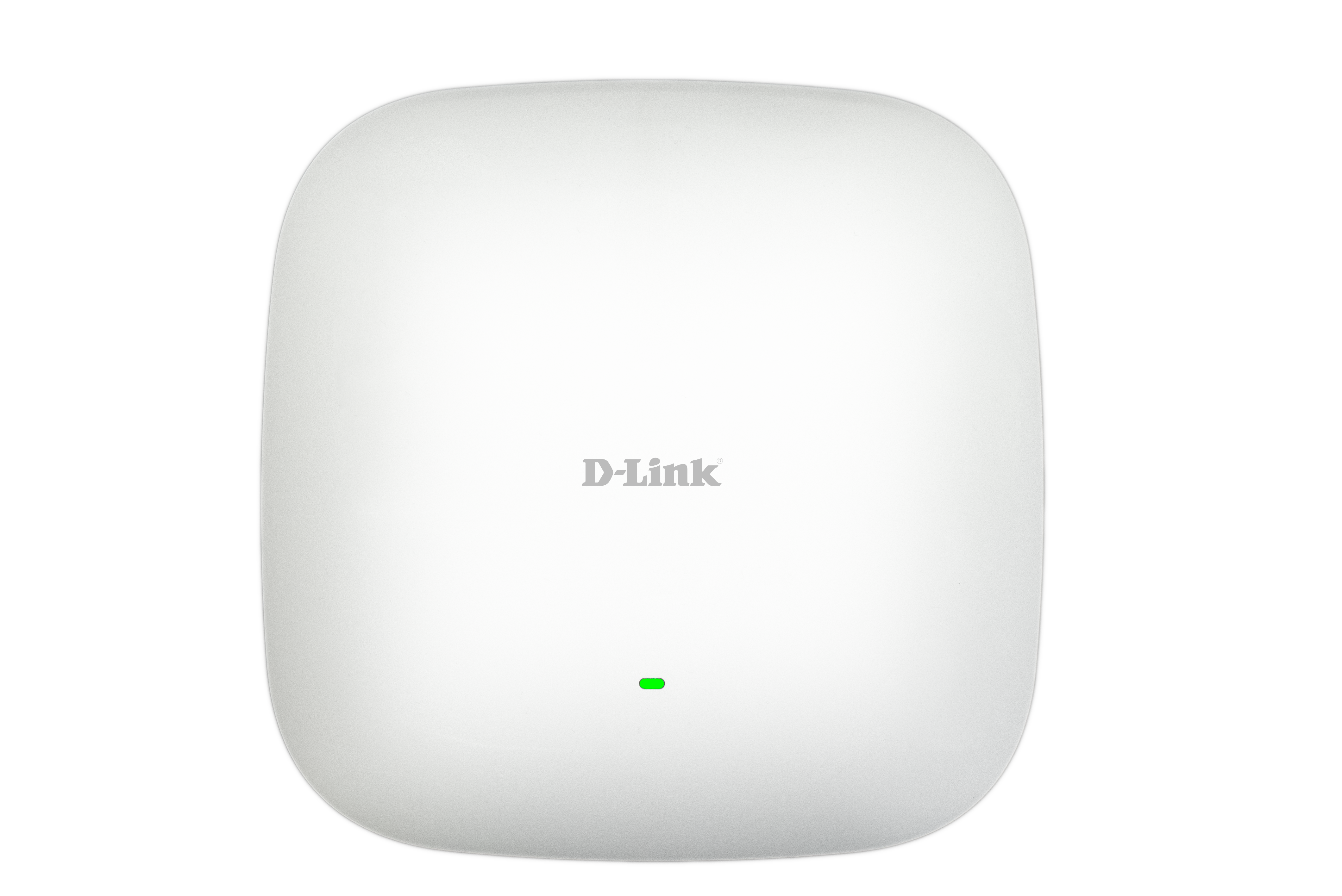Wi-Fi6・Wi-Fi6E・Wi-Fi7、今選ぶならどれ?
法人ネットワークの賢い選び方

・「無線LANアクセスポイントを更新する時期が来たけれど、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7のどれを選べば良いのか...」
・「最新規格は魅力的だが、価格や端末対応を考えると迷ってしまう」
・「PCはWi-Fi 6E対応になったが、無線LANアクセスポイントまで替えるべきか?」
無線LANは数年おきに新しい規格が登場します。性能は確かに向上しますが、法人環境では"最新"が必ずしも"最適"とは限りません。
重要なのは、コスト、端末対応、業務要件を踏まえ、自社にとって最も適した規格を選ぶことです。
1. なぜ規格の選定で迷うのか
規格進化が早いため
Wi-Fi6(2019年)、Wi-Fi6E(2021年)、Wi-Fi7(2024年)と短期間で進化しています。
Wi-Fi6とWi-Fi6Eは、規格としてはほぼ同じですが、6GHz帯対応という非常にインパクトのある進化を遂げています。
PCが新しい規格に対応する時期も遅れがちで、普及機といえる安価なPCのリリース時期も遅れがちだったことも、規格選定の際に迷いを生む要因になっていたと考えられます。
少し脱線しますが、次のWi-Fi8(802.11bn)は、最初のドラフトがまもなく発表される見通しで、IEEEの承認は2028年3月といわれています。
実際には、規格の承認は2029年〜2030年にずれ込むという話もあり、Wi-Fi 8対応PCが普及期を迎えるまでには、まだ猶予がありそうです。
Wi-Fi 6Eの急速普及
PCを見ると、現在のPCで最も対応機種が多い規格はWi-Fi 6Eです。
2025年8月20日の価格コムで調べたところ、法人向けを想定した以下3つの条件で絞り込むと、540機種が該当しました。
【絞り込み条件】
13〜14インチサイズのノートPC、Windows 11 Pro対応、CPUはIntelまたはAMD
- Wi-Fi 6:540機種中39機種(7.2%)、最低価格 69,367円(Inspiron 14 Core 3 100U・8GBメモリ・512GB SSD)
- Wi-Fi 6E:540機種中419機種(77.7%)、最低価格 72,800円(Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD)
- Wi-Fi 7:540機種中81機種(15.1%)、最低価格 134,962円(Dell Pro 14 Plus Ryzen 5 220・16GBメモリ・256GB SSD)
現在は、8割近くがWi-Fi 6E対応PCであり、価格もWi-Fi 6対応PCとほぼ同程度です。
Wi-Fi 7対応PCは全体の15%ほどに増えてきていますが、ハイエンド機が中心です。例に挙げたDell社のPCも、SSDを2倍に増やすなど仕様を上げると、すぐに15万〜20万円を超えてしまうでしょう。
無線LAN更改にあたり、最新のWi-Fi 7を導入したい場合でも、無線LANアクセスポイントはWi-Fi 7対応製品が高止まりしており、PCも過剰スペックで高価な製品が多い点は、規格選定で迷う要因といえます。
Wi-Fi 7の性能とコストのギャップ
先に述べた通り、Wi-Fi 7は大幅な高速化や低遅延が可能ですが、無線LANアクセスポイントは依然として高価で、対応PCもハイエンド機が中心です。
規格としては進化しており、6GHz帯対応による速度向上や、2.4GHz・5GHz・6GHzを同時に利用できるMLO機能など、高速化の恩恵を確かに受けられる要素があります。
デザイン会社や映像制作会社、一部のソフトウェア会社など、Wi-Fi 7の高速化メリットを活かせる企業にとっては、導入効果は大きいでしょう。
しかし、そうした業種以外では導入メリットを感じにくく、新しい規格であっても導入に躊躇する企業が多いのは、Wi-Fi 7対応の無線アクセスポイントやPCが依然として高価なためと考えられます。
こうした迷いが生じやすい状況の中で、どの規格を選ぶべきか判断する際の一助になればと、本コラムを執筆しました。参考にしていただければ幸いです。
2. Wi-Fi 7とWi-Fi 6/6Eの違いは?
Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7の違いについて触れたいと思います。
Wi-Fi 6とWi-Fi 6Eは、規格上はいずれもIEEE 802.11axであり、機能面も同じです。ただし、Wi-Fi 6Eでは6GHz帯が無線LANの周波数帯として利用できるようになった点が、大きな進化であり明確な違いです。
Wi-Fi 7は、Wi-Fi 6/6Eと比較してさらに進化しており、最大チャネル幅の拡大や変調方式の効率化に加え、3つの周波数帯を同時に使って通信するマルチリンクオペレーション(MLO)への対応など、速度改善を重視した進化となっています。
以下の表に違いをまとめましたので、ぜひ確認してみてください。
| Wi-Fi6 (IEEE 802.11ax) | Wi-Fi6E (IEEE 802.11ax) | Wi-Fi7 (IEEE 802.11be) | |
|---|---|---|---|
対応帯域 |
2.4GHz / 5GHz |
2.4GHz / 5GHz / 6GHz |
2.4GHz / 5GHz / 6GHz |
最大チャネル幅 |
最大160MHz |
最大160MHz |
最大320MHz |
最大理論速度(※1) |
約9.6Gbps |
約9.6Gbps |
約46Gbps |
主な変調方式 |
1024QAM |
1024QAM |
4096QAM |
主要機能 |
OFDMA、MU-MIMO(DL/UL)、BSS Coloring、TWT、DFS(5GHz帯利用時) |
Wi-Fi6機能に加えて、 |
MLO(Multi-Link Operation)、MRU(Multi-RU)、 |
普及状況(2025年8月現在) |
現在最も普及している。互換性と安定性に優れる。コストも安定している。 |
法人PCの約7割が対応済みで、原現在の普及中のモデル。無線AP価格はWi-Fi6製品に近しい価格帯まで下落し、PCも安価なモデルが出てきている。 |
導入初期段階。無線APは高価、PCもハイエンド機中心に出てきている。特定業務向けでは導入効果は大きい。 |
- ※
1:最大理論速度は規格値であり、実運用では環境や端末性能により異なります。
【DFS(Dynamic Frequency Selection)とは】
DFSは、5GHz帯でレーダー波(気象レーダーや航空レーダー)と干渉しないよう、自動的に周波数を切り替える機能です。
法人ネットワークでは5GHz帯を利用する場面が多いですが、DFS対象チャネルを使用すると、レーダー波検出時に数十秒間通信が中断されることがあります。
6GHz帯(Wi-Fi6E/7)はDFS対象外のため、通信の途切れを避けたい業務や、安定性を最優先する場面では有効な選択肢になります。
【機能差が法人利用に与える影響】
・OFDMA(Wi-Fi6以降):多数接続環境での遅延抑制に有効。
・MU-MIMO強化(Wi-Fi6→Wi-Fi7):上り通信も複数同時接続が可能になり、双方向通信が多い業務に最適。
・6GHz帯利用(Wi-Fi6E/7):干渉が少なく、大容量転送や映像配信に安定性を提供。
・MLO(Wi-Fi7):複数帯域の同時利用で速度・安定性を両立し、遅延を最小化。
・4096-QAM(Wi-Fi7):データ効率を向上し、大容量ファイルや高画質映像の転送を短時間で実現。
3. どの規格を選ぶべきかの判断基準
無線LANアクセスポイントを更新する際、どの規格を選ぶかは利用環境や目的によって異なります。
例えば、すぐに更新が必要な場合はWi-Fi 6Eが最も現実的です。6GHz帯を利用できることで混雑を回避でき、法人向けPCの対応率も高く、価格もWi-Fi 6と大きく変わりません。オフィスの更新やクラウド業務、映像会議の多い職場には適しています。
一方、映像制作やイベント会場、AR/VRのように高速かつ低遅延が業務成果に直結する環境では、Wi-Fi 7を選ぶ理由が十分にあります。MLOや4096-QAMといった新機能により、従来では難しかったレベルの安定性と処理能力が得られるからです。
また、「今はWi-Fi 6Eにしておき、将来的にWi-Fi 7へ移行する」という段階的な更新も有効です。長期的にネットワークを順次入れ替える計画では、このアプローチがコスト効率と将来性のバランスを取りやすくなります。
さらに、古い端末やレガシー機器が多い環境では、あえてWi-Fi 6やWi-Fi 6Eを選び、互換性を優先する判断もあります。最新規格を導入しても端末側が対応していなければ十分な効果が得られないため、既存資産との整合を重視することも重要です。
【業務別おすすめ規格マトリクス】
| 業務・利用シーン | 推奨規格 | 推奨理由 |
|---|---|---|
一般的なオフィス業務 |
Wi-Fi 6E |
PC対応率が高く、6GHz帯で混雑回避可能。無線APやPCの価格はWi-Fi6より若干高価だが、普及価格帯といえるところまで下がってきている。 |
営業・支店拠点 |
Wi-Fi 6E |
高速かつ安定した通信。互換性も高く拠点統一しやすい |
教育機関・会議施設(多数端末同時接続) |
Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 |
OFDMAで多数接続に強く、6GHz帯で干渉を低減。またWi-Fi 7であれば、MLOによる3帯域同時通信で通信が安定。 |
映像制作・放送業務(高解像度映像編集・配信) |
Wi-Fi 7 |
320MHz幅・4096-QAMで大容量データを短時間転送 |
イベント会場・展示会(多数同時接続、リアルタイム配信) |
Wi-Fi 7 |
MLOで複数帯域を活用し、安定性と速度を両立 |
AR/VRや遠隔制御(低遅延必須) |
Wi-Fi 7 |
MLOと低遅延設計でタイムラグを極小化 |
レガシー機器が多い環境(古い端末利用) |
Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E |
互換性重視で移行負担を軽減 |
4. 導入時の注意点
新しい規格の無線LANを導入する際には、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。
まず確認したいのは、端末側の対応状況です。無線LANアクセスポイントを最新化しても、接続するPCやスマートフォンが非対応であれば性能を発揮できません。導入前に社内端末の対応規格を把握しておくことが大切です。
次に、6GHz帯の利用条件です。国内では屋内専用といった規制があり、利用環境によって制限がかかる場合があります。導入前に規制の内容と自社環境が適合しているか確認しておきましょう。
また、DFS(Dynamic Frequency Selection)の影響にも注意が必要です。5GHz帯の一部チャネルでは、レーダー波を検出すると数十秒間通信が止まることがあります。業務に影響を与える可能性がある場合は、DFS対象外となる6GHz帯を積極的に活用するのが有効です。
さらに、電波特性も無視できません。6GHz帯は高速通信に向く一方で、壁や障害物に弱く減衰しやすい特徴があります。オフィスの間取りや利用人数に合わせて、無線LANアクセスポイントの設置場所や台数を計画することが重要です。
最後に、将来の拡張性も考慮しましょう。次世代規格の登場時に再度LAN配線やスイッチを入れ替えることにならないよう、マルチギガ対応のスイッチを選ぶなど、中長期的な視点で準備しておくことが望まれます。
5. まとめ
- 現状のバランス重視ならWi-Fi6E
性能・価格・普及率のバランスが良く、導入効果がすぐ得られる
- Wi-Fi7は目的次第で有力候補
高性能が業務効率や品質向上に直結する環境では大きな効果
- 規格選びは戦略的に
単に最新を追うのではなく、自社の業務要件・更新計画に合わせることが重要
D-Linkの無線LANアクセスポイントにも、Wi-Fi 6からWi-Fi 6Eモデルのラインナップがあります。
今後はWi-Fi 7対応の無線LANアクセスポイントの販売予定もありますが、現状の普及モデルであるWi-Fi 6やWi-Fi 6E製品をご覧ください。